社外取締役メッセージ
取締役会議長メッセージ|社外取締役 橘川 武郎
社外取締役としてガバナンスや経営の課題をアドバイス
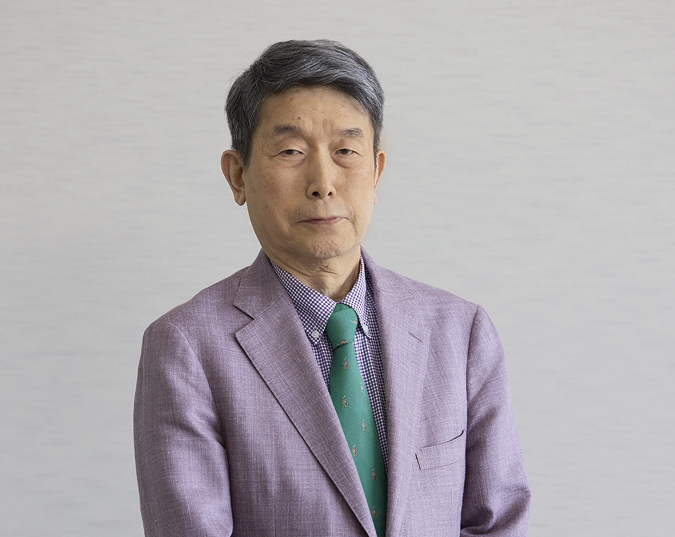
株式会社における社外取締役の機能は、監督とアドバイスに大別できると考えており、当社においては、いずれの機能も基本的にはきちんと作用しています。エネルギー供給責任の増大とカーボンニュートラルへ向けてのトランジションとが複雑に交錯する現在において、当社にとって最大の経営上の課題は、的確な投資ポートフォリオを設定し、それを実行に移すことです。この課題を遂行するプロセスにおいて、社外取締役はそれぞれの専門性を活かし、主に事業転換の方向性やリスク管理について、積極的に発言しております。
ただし、当社のガバナンス体制に問題がないわけではありません。事業のグローバル展開にもかかわらず、取締役・監査役は日本人だけで構成されており、国際性という点でのダイバーシティに欠けています。取締役・監査役間の情報共有も十分とは言えず、これらの点については改善の余地があると考えております。
当社が直面する最大の課題は、サプライサイドからの発想が強く、マーケットインの発想が弱いという点です。2040年へ向けての日本のエネルギー需要は、電力は増加し、ガスは横ばい、石油は減少となります。そのような中、当社は拡大する電力市場におけるビジネスチャンスの追求について、遅れをとっています。新しいエネルギー事業の成否は、オフテイカーの有無によって決まります。アンモニアとブラックペレットという石炭火力事業者をオフテイカーとする2つの切り札を有しながら、現状の当社は、石炭火力事業者のカーボンニュートラル化を先導する担い手となるという覚悟に欠けています。また太陽光・地熱発電に関して、他社にない経験と資産を擁しながら、再生可能エネルギーを自社のカーボンニュートラル戦略の中に、うまく組み込めていません。これらの問題を解決するためには、電力市場を対象に、マーケットインへの発想の転換を進める必要があると考えております。
カーボンニュートラルとは、CO₂排出自体をゼロにすることではなく、CO₂の排出と回収・吸収を等しくし、CO₂排出増加のネットゼロを実現することです。CO₂回収の増大においてはCCUSの加速が肝要ですが、当社はCCUSに関して、高いポテンシャルを有しています。電力需要の増大から化石燃料の使用は今後も継続すると見込まれますが、当社はエネルギーの供給責任を果たしながら、そのトランジションをも先導するという「崇高な二正面作戦」を展開する力を、十分に持ち合わせています。酒井新社長のもとで、この力の発揮に期待しております。
指名・報酬諮問委員会委員長メッセージ|社外取締役 鈴木 純
新社長選任や持続可能な人財戦略へ、社外の多様な視点から提言
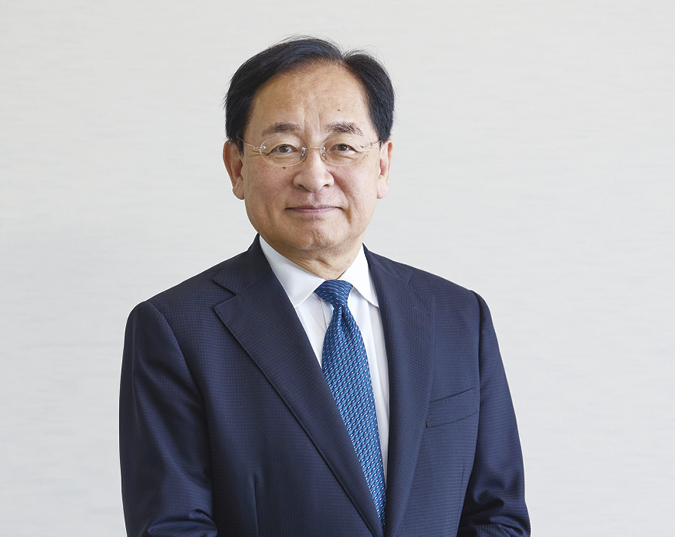
私が社外取締役に就任した2023年から、社長交代・選任を意識し、サクセッション、トップ任命、チーム構成などに当委員会がどのように関わるかを常々考えておりました。社内には社長になることができる資格を持つ上席執行役員以上の役員が多くいます。外部の専門会社による360度評価などのデータも参考にしながら、委員会では必要な能力や資質などを踏まえて2024年秋から議論を重ねました。そして、2025年1月に委員会全員で合意し、2月の取締役会で社長の決定に至りました。
候補者の絞り込みに当たり、委員会では3つの観点を重視しました。1つ目は「バランスの取れた経営能力」です。基盤の燃料油事業で収益を上げつつ、カーボンニュートラルへの移行に挑戦するという将来に向けた投資を実行できることです。2つ目は「包容力のあるリーダーシップ」です。不確実な環境下で社員が安心して活躍できるように支え、ステークホルダーからの支援を得ることです。3つ目は「日本のエネルギー政策への貢献」です。当社が日本のエネルギー政策にいっそう貢献できる体制を整えることです。社長が当社の意思決定やオペレーションを行い、社長経験者である会長が政策面で強い意見を言うことで、日本のエネルギー政策を引っ張っていくような立場になっていただくこと、社長と会長はそのような組み合わせがよいのではないかという議論も行いました。
当社では現在、より長いスパンで継続性のある人財育成を進めています。今回の新体制の次世代、次々世代のチーム構成を見据え、どのような人財をどのポジションに就けていくかということも当委員会で議論するようになってきています。人財の流動性がますます高まる中で、若手や中堅社員にしっかりと考えられたキャリアパスを示すことは、社内人財の育成とモチベーション向上につながるのみならず、当社で働きたいという社外の方へのメッセージにもなりえると思っています。
当社の企業価値を高めていくために、人財戦略は非常に重要な要素です。指名・報酬諮問委員会では、人財戦略の基盤となる人事制度から、取締役会では直接議論ができない役員の人事・報酬案件までを扱います。社外取締役は様々なバックグラウンドを持ち、それぞれの経験や知識をもとに、幅広い観点からの議論を行います。そして、執行側にフィードバックしたり、取締役会への諮問をしたりという、議論、提案、決定、モニタリングというサイクルを回すようにしています。会社の制度や仕組みは常に見直しを入れていくことが必要です。役員の人事・報酬制度や仕組み、あるいは役員の人事・報酬案件に対して、執行側の事情や考えも理解しながら、最適と考えるアドバイスを入れることを、今後も継続していきます。
社外監査役メッセージ|社外監査役 手塚 正彦

当社のコーポレートガバナンスの現状に対する評価
監査役に就任してからの1年を振り返ると、取締役会、監査役会などにおいて、社外役員と執行側との間で建設的かつ活発な議論が行われていることがとても印象的でした。社外役員がその職責を果たすためには、必要な情報を得る機会が確保されること、取締役会や監査役会で自由に発言できる環境が整えられること、社外役員の意見を経営改善に活かそうとする会社の姿勢、そして社外役員が適切な能力を有することが求められます。当社では、これらの要素が高いレベルで満たされており、「社外役員が職責を果たしているか」という観点から、当社のコーポレートガバナンスは健全に機能していると評価しています。
監査における重要なテーマと活動
石油業界は、カーボンニュートラルの実現に向けて、きわめて難しい経営の舵取りを求められる業種です。当社においても、燃料油をはじめとする既存事業の収益性を確保しつつ、次世代電池向け固体電解質などの新規事業において成果を上げる必要があります。また近年、千葉事業所における労働災害事故の発生や、東亜石油(株)や昭和四日市石油(株)における製品試験の不適切行為など、安全およびコンプライアンスに関する重大な問題が続発しました。これらの課題や問題に対して当社が適切に対処できているかどうかは、監査上の重要なテーマであり、私自身も千葉事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)を訪問し、それぞれの現場が課題や問題に適切に対処していることを確認しました。
対話と現場を知ることを通じた監査の実効性の向上
監査役の役割は、企業経営の「方針、仕組み、人」に精通し、企業が適切な方針のもとで経営の仕組みを整備し、その仕組みを適切な人が適切に運用しているかを確認することです。もし企業が誤った方向に進んでいる場合には、経営者に対して強く是正を求める必要があります。そのためには、当社の経営者や社員との対話を深め、自ら現場を理解することが重要です。私も対話や現場訪問を通じて現場の状況を的確に把握し、経営者と社員が共通の認識をもって正しい方向に進んでいることを確かめることで、監査の実効性を高め、当社の健全な成長に貢献してまいります。