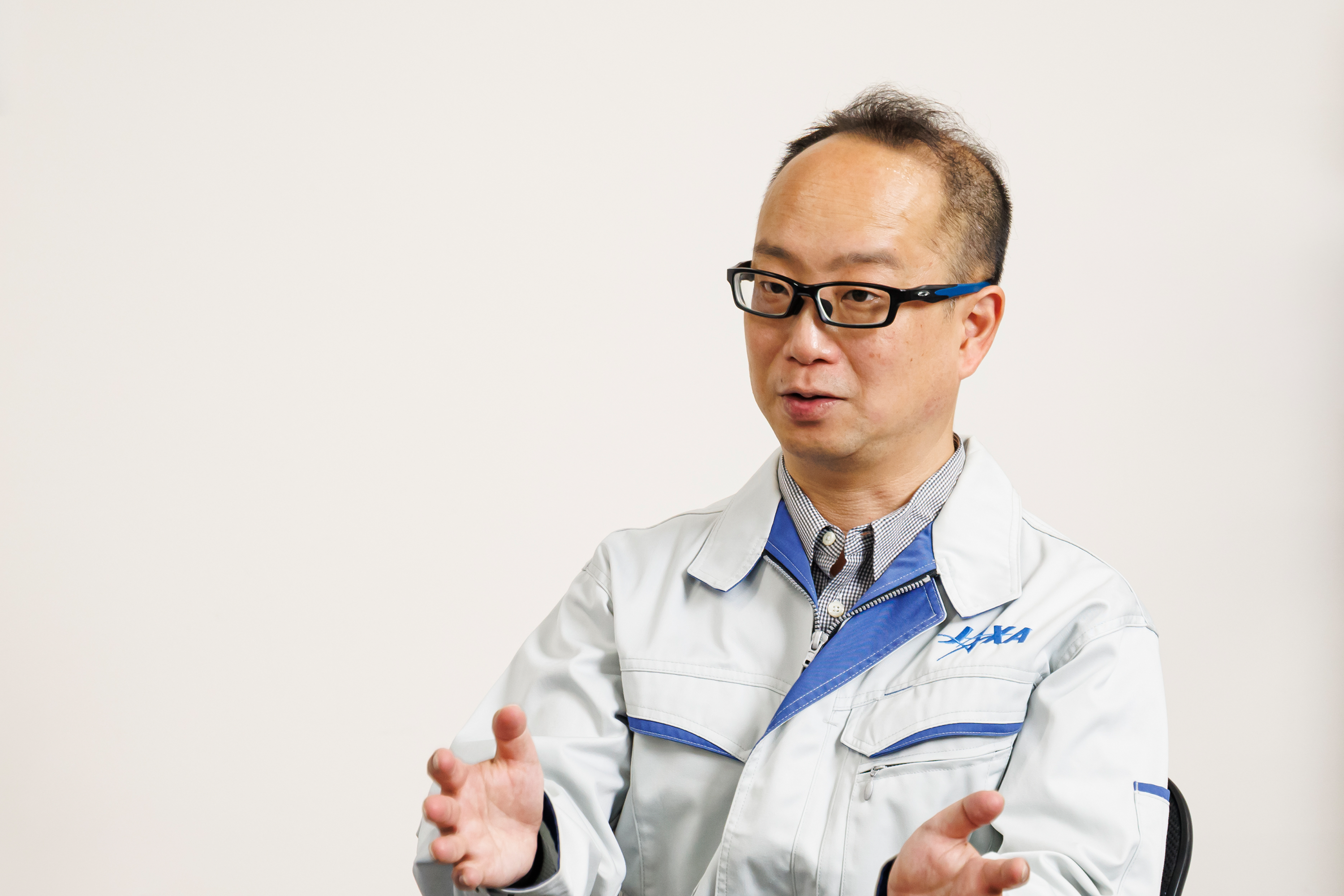「3接合太陽電池」の低コスト化を企図。CIGS太陽電池の実績を持つ出光に白羽の矢
今回、SDXでは、もう1社の供給メーカーと出光興産、JAXAの3者が共同で開発した3層構造の太陽電池「PHOENIX」と、出光興産のCIGS太陽電池単体での実証が、並行して行われる。
T.OKUMURA
「これまで、1種類のウェハ(半導体材料でできた薄い円盤状の基盤)上に3層分の薄膜太陽電池を積層させた『3接合太陽電池』を運用してきましたが、値段が高く、科学衛星など性能重視の衛星に使用を限定せざるを得ませんでした。そこで、上部の2層は従来のまま、3層目として、より低コストでの製造が可能なCIGS太陽電池を接合するアイデアを実証することになりました。これが『PHOENIX』です。具体的には、薄膜2接合太陽電池とCIGS太陽電池を貼り合わせています。3層目にCIGS太陽電池を用いると決まった時点で、豊富な開発経験を有している出光さんに協力を打診しました」
H.TOMITA
「宇宙空間に耐え得るものを作る上では、どういった課題があるのか、どういったアプローチが選択肢になり得るのか。当初は、前提条件の部分で考えが及ばず、多くのことをJAXAさんに教えていただきながら試験を重ねました。また、打合せでJAXAの方々から飛び出す“宇宙語”の意味が分からなくて、その場で質問したり後から調べたりすることも多かったですね」
T.OKUMURA
「宇宙空間では、地球上とは全く異なる環境条件に対応する必要があります。最も特徴的なのは、強い放射線に絶え間なくさらされること。また気温も、約マイナス100℃からプラス100℃までの範囲で大きく変化します。とくに放射線は、太陽電池の性能劣化に直結するため、『放射線に耐えられるものづくり』を念頭におく必要があるのです。このあたりの感覚は、宇宙用途の開発経験がないと初めはなかなか理解してもらいにくい部分でもあります」
「地上用」と「宇宙用」。環境の著しい乖離からくるギャップを乗り越えて
H.TOMITA
「たしかに、宇宙仕様のスタンダードを理解することが、最初のハードルだった気がします。また、信頼性の面では厳格さが求められる一方で、方法論については私たちの認識では宇宙向きとは思えないアプローチが、実は有効であることが分かり、意外に感じる場面もありました。先ほどあったようにPHOENIXは2接合太陽電池とCIGS太陽電池を貼り合わせているのですが、『接着剤で貼り合わせたら良いのでは?』というアイデアを伺った時は驚きましたね。『溶接でなくて良いんだ!』と(笑)。接着剤に限らず、宇宙環境で使って問題ないかどうか、使う場合はどういった点に注意して使わないといけないのか、JAXAさんの中でしっかり検証・蓄積されている。JAXAさんには宇宙用途のものづくりにおいて配慮すべき点を一つひとつ教えていただくとともに、当社の太陽電池の様々な信頼性評価試験も実施していただきました。その過程で、当社のCIGS太陽電池は徐々に宇宙用途になり、“地球人”であった私たち自身も“宇宙語”を理解する“宇宙人”に少しずつ近づくことができました(笑)」
T.OKUMURA
「電気がないと、人工衛星は動きません。そのため、太陽電池は人工衛星にとって極めて重要なパーツです。また、一度打ち上げてしまったら、故障が起きてもすぐ交換に行くことができません。だからなおのこと、高い信頼度が求められるのです。太陽電池の場合、まずは2cm角ほどのセルを用いて地上で放射線の照射試験を行い、次に宇宙空間で実証。それもクリアしたら実際の製品と同等サイズのセルでの評価、最終的にはセルを複数組み合わせたパネルでの評価といったように、ステップ・バイ・ステップで開発が進んでいきます。打ち上げ時の振動環境に耐えられるか、軌道上の熱サイクル環境に耐えられるか、といった観点での検証も重要です」
未知の領域へ。実証に募るのは不安よりも大きな期待
SDXでは、PHOENIXに加えて、CIGS太陽電池単体での実証も行う。これは、出光興産の働きかけにより実現した。
H.TOMITA
「率直に、CIGS太陽電池単独での実力を見極めたいとの思いから、打診しました。常に実績が問われる世界なので、お客様への提案の場でも『実際に、宇宙に飛ばしたことあるの?』と必ず聞かれます。PHOENIXの上部2層は、短波長の光の吸収に優れているので、3層目のCIGS太陽電池では主に長波長の光を受け取ります。一方、CIGS太陽電池単独の場合は短波長から長波長まで全ての光がCIGSに届きます。SDXの結果については、PHOENIXと単独、どちらについても期待が不安を上回りますね。宇宙空間で何が起こるのか予想がつかない分、どちらの実証結果も楽しみです」
T.OKUMURA
「PHOENIXは非常に難易度の高い開発でしたが、2接合太陽電池の供給メーカーともうまく協働し、SDXに搭載できるレベルにまで仕上げていただきました。また、CIGS太陽電池単独での搭載はPHOENIXの軌道上での動作を検証するという重要な意味もあります。その実現のために宇宙で使用可能なセルをスピーディーに提供していただき、感謝しています」
D.OGAWA
「そのお言葉は嬉しいです!研究所には、パートナーの期待に応えようと、協力して動けるメンバーがそろっています。高いハードルにもチームの総力で挑み、なんとしても達成しようとする—いわば『有事に強い』のは、出光らしさかもしれません。また、CIGSそのものは、当社の高機能材事業領域発の『マテリアル』ですが、私たちが今手がけているのは、CIGS太陽電池という『デバイス』です。出光の中でもユニークな位置づけにあると認識しているので、SDX実証の結果を次なる展開につなげていきたいです」
H.TOMITA
「開発期間を通して、JAXAさんにはずっと伴走していただきました。試験環境用装置の提供から、試験の実施に際しての助言、さらには結果をいかに読み解くか。どこをとっても、当社のみではなし得ませんでした。関わる前は、世界のJAXAに敷居の高さを感じていましたが、当初からフランクに議論ができたこともありがたかったです。『宇宙用CIGS太陽電池の社会実装を実現させたい』との想いはJAXAさんからも非常に強く感じており、この共通項があればこそ、今回の開発もうまく進められたのだと思っています」

 JAXA
JAXA 出光興産株式会社
出光興産株式会社 出光興産株式会社
出光興産株式会社