Idemitsu Art Award 2024 グランプリ受賞者インタビュー
たどってきた印象のかけらを内包したコラージュ、
「Idemitsu Art Award 2024」グランプリ 笹本明日香
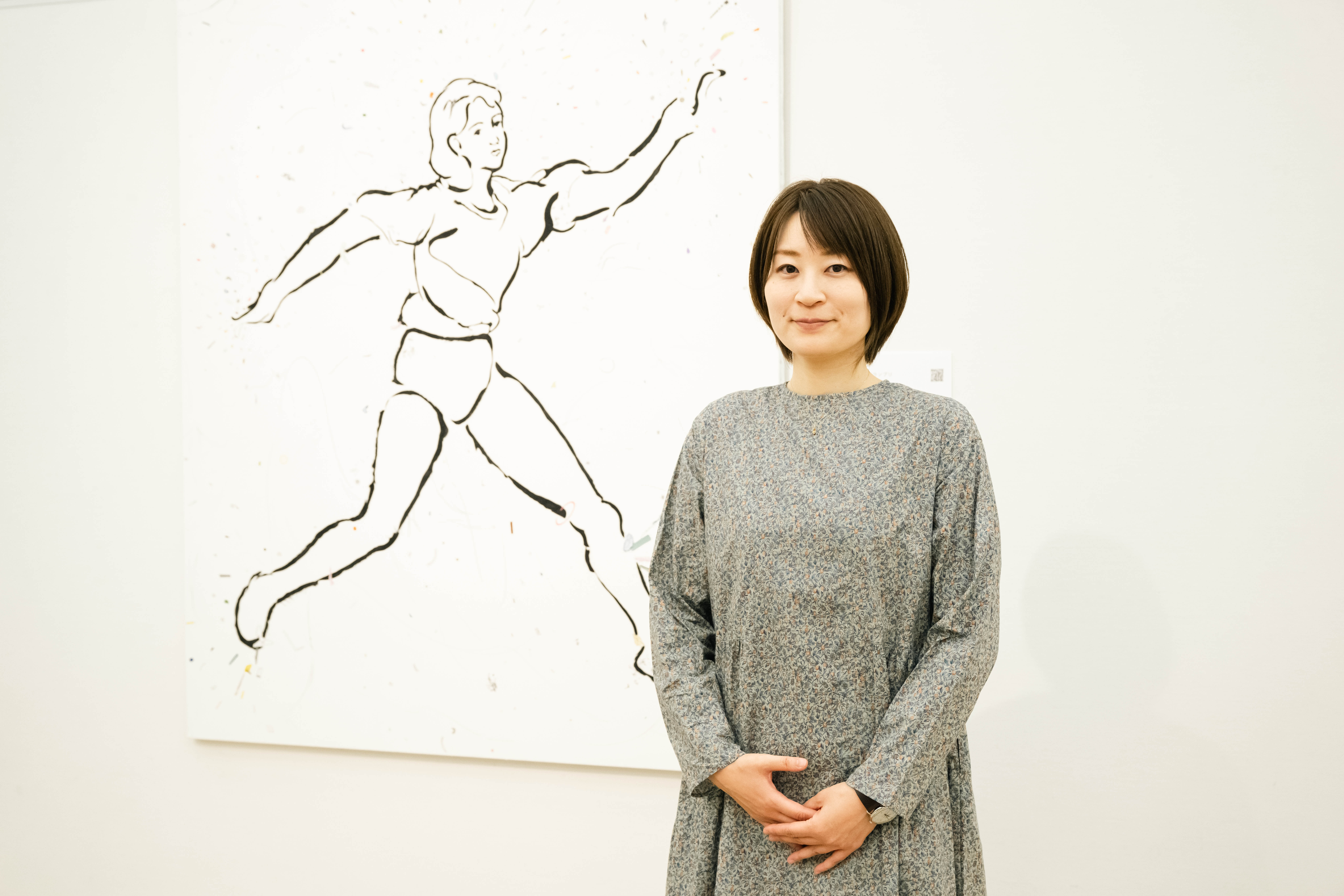
若手作家の挑戦の場となってきた出光興産主催の「Idemitsu Art Award」。40歳以下の作家による平面作品を対象とした公募制の美術賞で、前身の「シェル美術賞」から53回目、「Idemitsu Art Award」に改称されてからは3回目を数える。
今年度の「Idemitsu Art Award 2024」では、昨年度を上回る応募総数734名922点という激戦の中、笹本明日香(ささもとあすか)さんの「アクセス」がグランプリに決定した。今年度の受賞・入選作品などが紹介される「Idemitsu Art Award展 2024」を前に、笹本さんに受賞作への想いや今後の制作についてお話をうかがった。
マンガへの憧れから図像への関心へ
今年度の審査員は、大浦周氏(埼玉県立近代美術館主任学芸員)、正路佐知子氏(国立国際美術館主任研究員)、竹崎瑞季氏(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館キュレーター)、菅亮平氏(美術作家/広島市立大学芸術学部講師)の4名。
全員一致で、笹本明日香さんの「アクセス」がグランプリに選ばれ、300万円が授与された。2008年に多摩美術⼤学美術学部絵画学科油画専攻を卒業した笹本さんは、東京を拠点に作家活動を続けている。
─ 笹本さんはアラスカ生まれだそうですね。アーティストになった経緯を教えていただけますか?
アラスカには父の仕事の関係で、生まれてから2年ほどしか住んでいないので大きな話はないんです。ただ、姉兄から聞く当時の話や写真、外国のおもちゃを持ち帰って遊んだ影響は少なからずありますね。
子供の頃から絵が好きで、マンガやアニメ、ゲームの影響を受けて育ちました。まねごとでマンガを描くうちに図像に興味が沸き、美術大学を志すようになっていきました。多摩美術大学で油画を専攻したのは、中学時代に美術部で油絵の経験があり、美術予備校の見学時に油画科は表現に幅があると感じたからです。
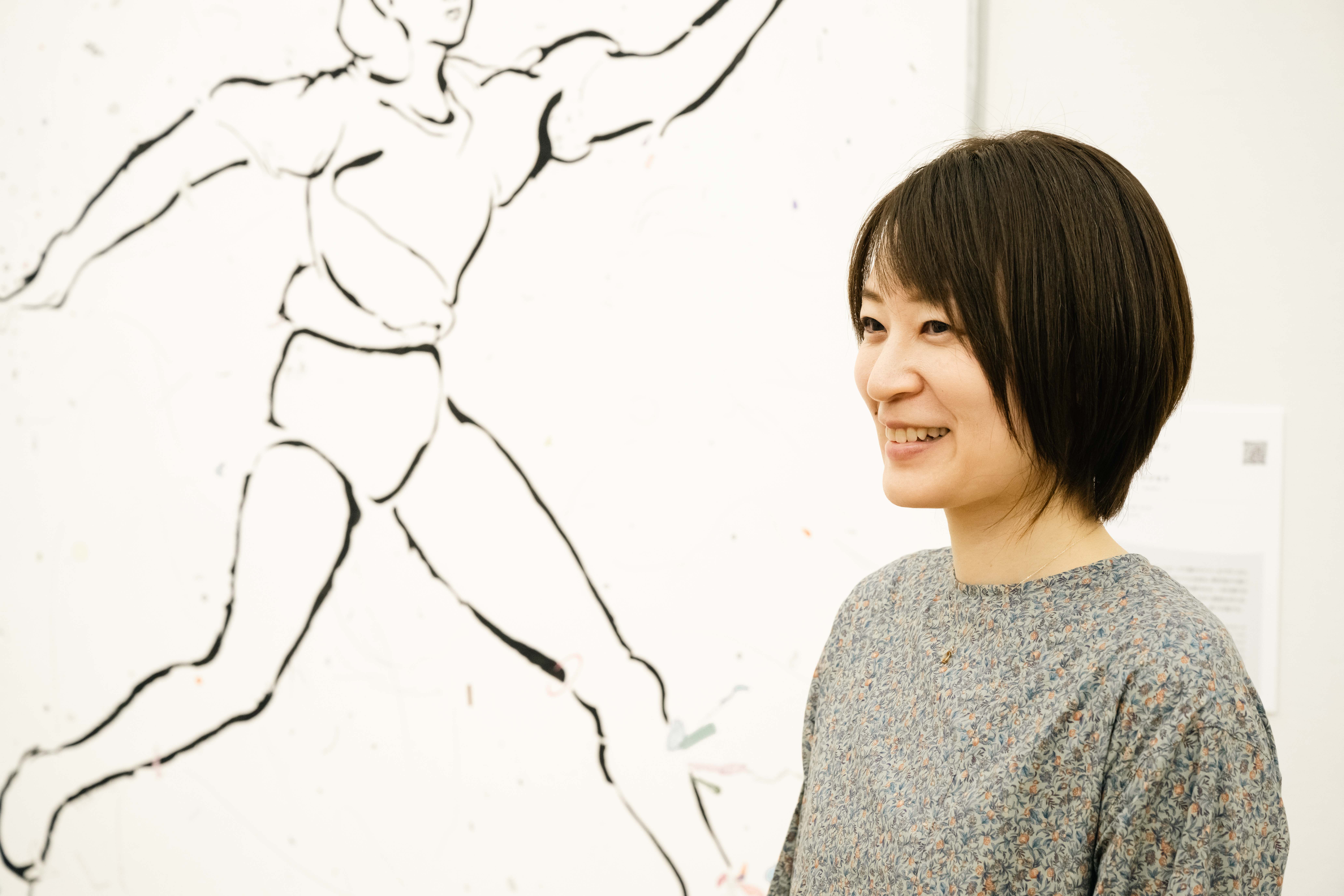
笹本明日香さん
─ 在学中はどのような制作を行っていたのでしょうか?
油絵という手法で制作していく中で、自分にとってさらにベストな表現方法はないかと模索し始め、紙粘土に絵の具を塗り込んだものや布を画面に貼り付けたり、雑誌そのものに何かを貼ったり、さまざまなアプローチを試みました。
その中で教科書や参考書の説明図など、印刷図版が自分にインパクトを与えてくれるものとして再認識し、自分に影響を与えているものを引用・コラージュするという手法を用いるようになりました。
─ 今回、Idemitsu Art Awardに応募した理由を教えてください。
美術予備校でシェル美術賞を知り、大学でも同級生が精力的に挑戦して入選・受賞する人もいて、アートシーンで闘う作家を知る情報源にもなっていました。卒業後も制作のモチベーションとしてさまざまな公募展に挑み、入選経験もあります。
けれど、シェル美術賞およびIdemitsu Art Awardでは入選したことがなく、今回で年齢制限のラストチャンスだったため、受賞を目標に応募しました。
落選した過去作をコラージュ作品にトランスフォーム
─ 受賞作はどのように構想したのですか?
実は2年前にもIdemitsu Art Awardに大型のペインティング作品を3点出品したのですが、すべて落選してしまいました。今回は、そのうちの2点を使い、キャンバスを剥がして裏返しに貼り、ジェッソを塗ってその上に描いた作品を2点出品しました。
自分の手法としては、同一レイヤーに一枚の色面として絵具を描き重ねていくことに違和感があったので、今までずっと取り組んできたコラージュでいこうと決意して挑みました。2年前の落選という出来事も素材の一つと考える必然性を感じました。
─ 過去に取り組んだ時間も受け継ぎながら新しい画面をつくりあげたのですね。
はい。下地を作って真っ白にして、紙にドローイングする感覚で描きました。今までペインティング作品で、絵の具で下地を作ることを当たり前の過程としてやっていましたが、思い切って白い状態で制作した方がいいと判断しました。
大学卒業後、CM絵コンテライターの会社でPhotoshopを学んだ経験を機に、素材一つひとつにレイヤーがあるという捉え方が生まれました。今回の作品の白い画面は、Photoshopの「透明」を表す「レイヤーに何もない状態」に近いイメージです。
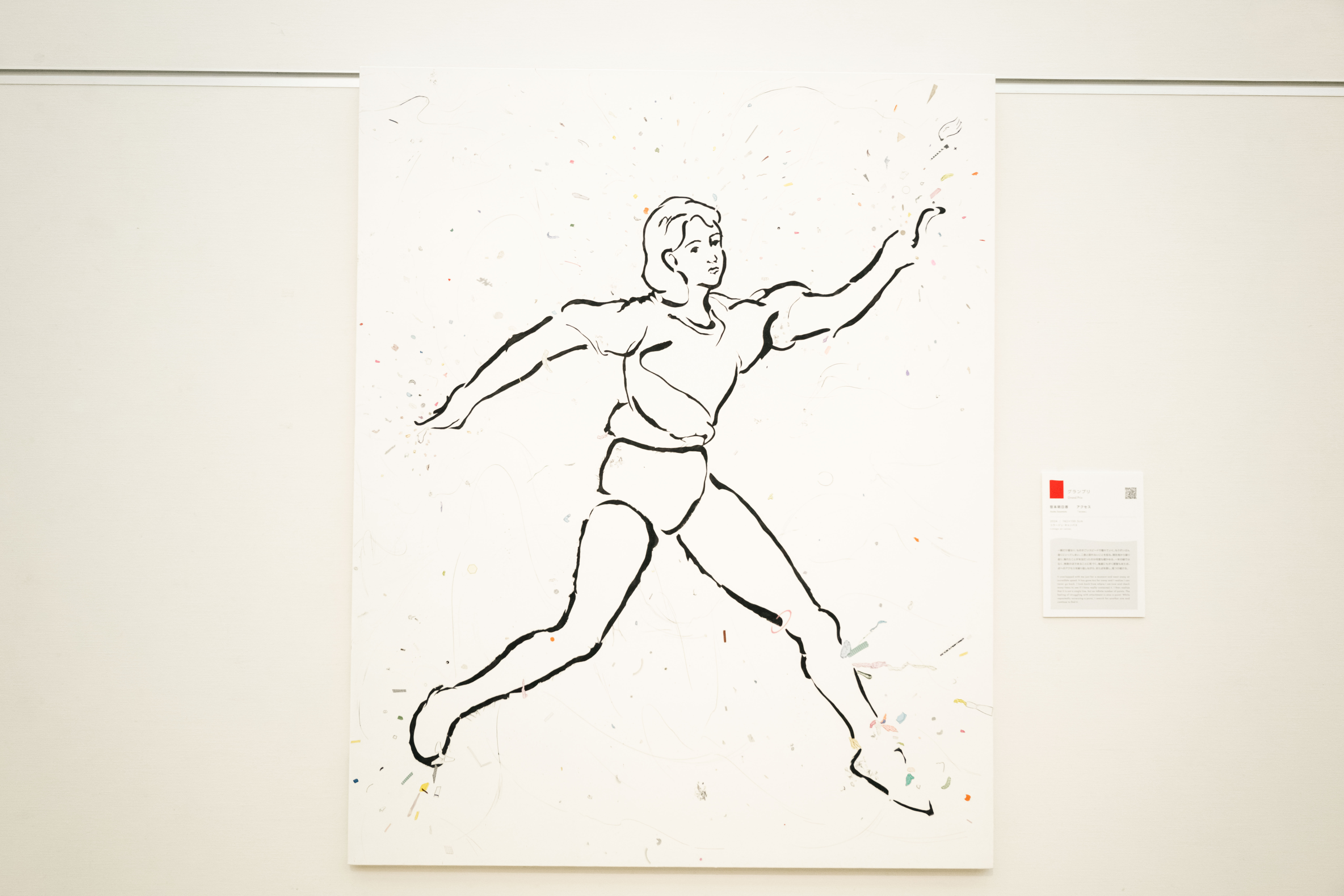
笹本明日香「アクセス」 2024年 162×130.3cm キャンバスにコラージュ
─ 人物像のモチーフはどのように選び取ったのですか?
兄が中学の頃に使っていた体育実技の教科書にあるイラストレーションをもとにしています。学生の頃からずっと強く印象に残っていて、この図像がもたらす記号性や、作り手の自我が切り離されている性質などからヒントを得ています。教科書の図像をそのまま使うのではなく、例えば、野球のページの腕と陸上のページの脚を部分的に組み合わせるなどして再構成しました。
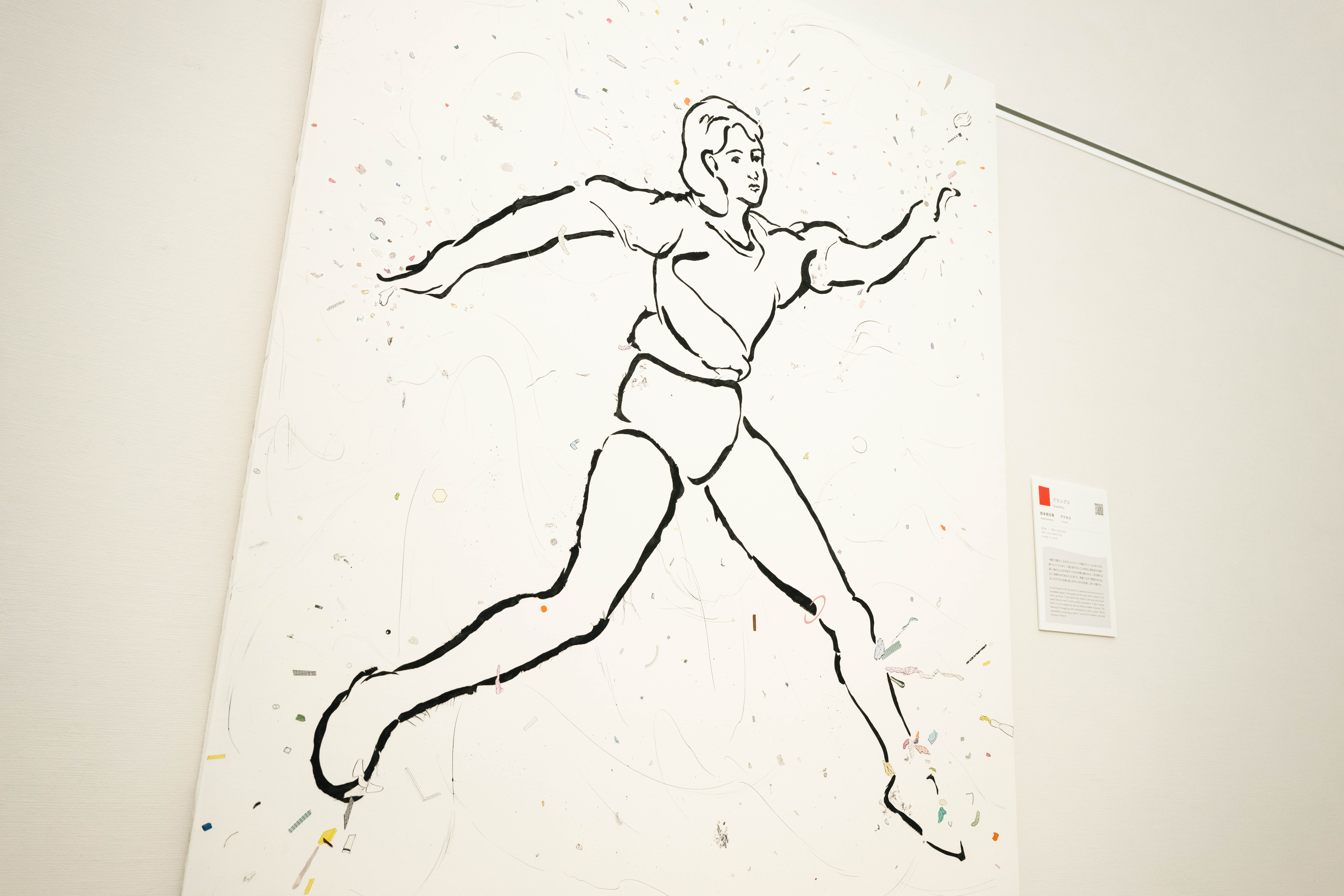
─ 体のねじれが面白く出ていますね。人物のねじれや体操着を着せた理由はありますか?
大人になって、学校という場所の独特さを思い返すことがよくあります。制服の匿名的、記号的な感覚とか。体操着もまた、体育という特殊な儀式を行うための記号として印象に残っており、体を動かす行為の象徴として用いたいと考えました。
筆で描いてストロークで表すのではなく、拡大コピーした下絵に合わせ、黒い絵の具で着色した布をハサミで切り、キャンバスに線画として貼り付けています。自分でも初めて見たうねりや表情になり、楽しかったです。
─ 人物のまわりに、印刷物などを切り抜いた小さな紙片がコラージュされていますね。
生活の隙間時間で気に入って切り貯めた素材を貼り付けています。子どもの頃に抱いていたマンガ家になりたいという幻想や執着、今まで影響を受けてきたもの、思い入れや出来事など、自分がたどってきたものを作品に落とし込んでいます。
漫画用のつけペンで線を描いたり、活用できなかったスクリーントーンを使ったり、実生活で食べたお菓子や日用品のパッケージ、以前に描いた自作の一部を貼ったり。今回の作品に使おうと思わずに集めたものも含まれています。

布で表現された人物の輪郭線。ところどころに糸のほつれを出している
─ パーツの配置には意図があるのですか?
ここにこのパーツを置いたらこちらに置きたくなるという欲求、あるいは置きたくないという反発に沿って配置しています。デザイン的にならないように、あるいは絵画的なバランスをあえて崩したり、物語性を部分的に出したりしました。
─ どのような判断でフィニッシュ(完成、終了)したのでしょうか。
最終日は徹夜でしたが、最後に、コラージュだけでなく、自分で描いた線も必要だと判断して線で描画しています。作品搬入の集荷が来るギリギリまで描いて送り出しました。
実は、応募したもう1点の作品の方が、コラージュの大きさや構成が作品の完成度として伝わりやすいかなと思っていたため、受賞のご連絡をいただいたときには、タイトルを聞くまでもう1点の作品が受賞したと思い込んでいました(笑)。
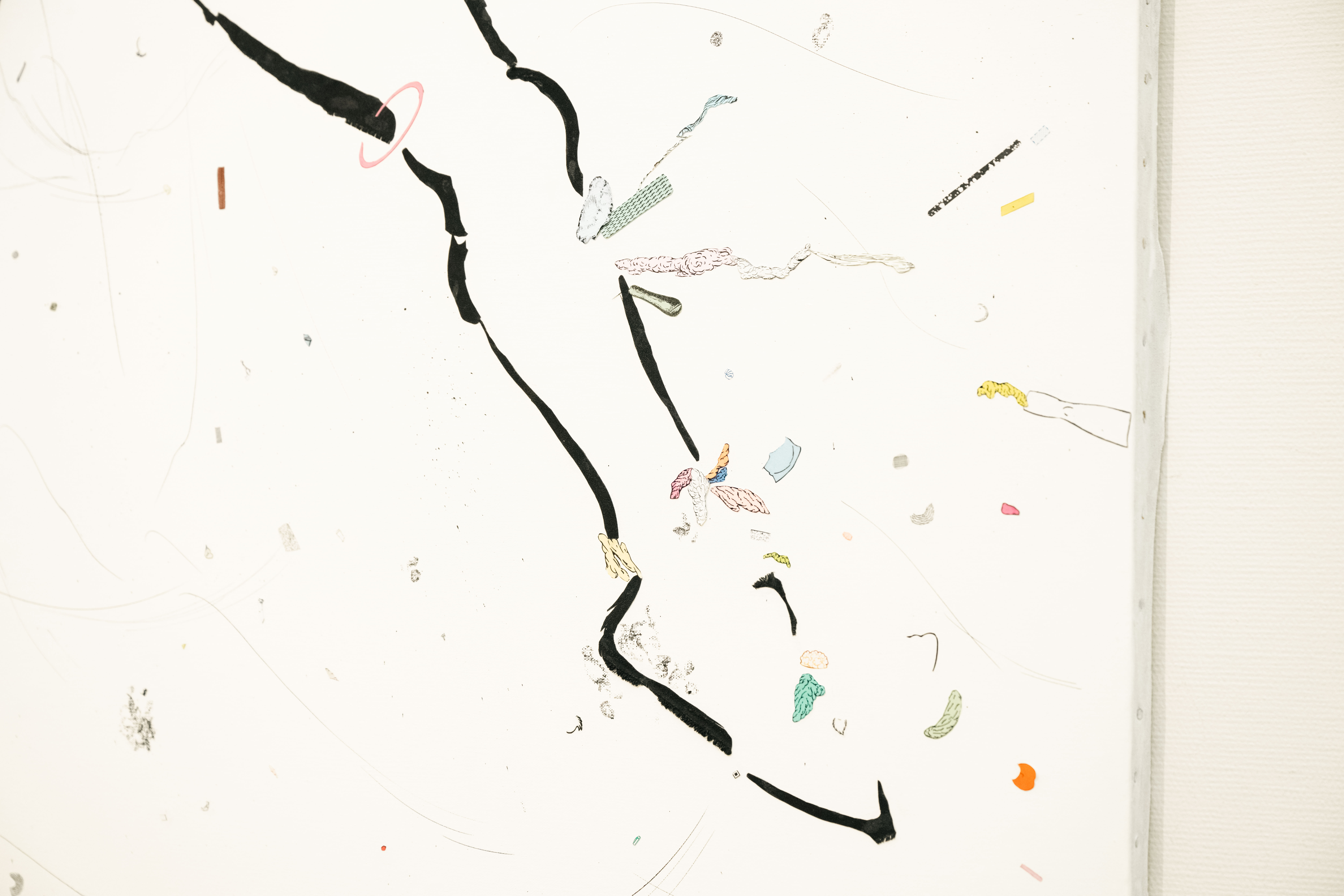
細胞が壊れて血液のように流れていくイメージを表現
手からこぼれ落ちる喪失感と、すでにそこにいるという両義性
─ 作品タイトルは「アクセス」。情報の渦に手を伸ばしているようにも見えますね。
そうですね。スペースデブリ(宇宙ゴミ)のようなものをイメージしています。自分が活用できなかったものや生活の垢、不純物や排泄物のようなものです。
年齢を重ねるごとに、あらゆる出来事が刹那的だと強く意識し、喪失感を抱くようにもなりました。時間の流れが早く、自分が風化してしまうような感覚も生まれ、忘れたくない、失いたくないものを掴もうとしても、この手から消えていくどうしようもなさみたいな……。
その一方で、自分が執着しているものは一体どこから来てどこへ行くのか。と考えた時に、自分の抱いてきた感覚や印象がもし実体化して蓄積したら計り知れない量になると想像し、失ったのではなく膨大にたまり続けた大きなデータベースに包まれているようにも感じられたのです。その大きな“水溶液”に自分が浸っているとも考えられるのではないかと。

─ ネガティブだけでなく、ポジティブでもあるという感じですか?
はい。いろいろな性質が同時に起きていて、掴もうとする執着や喪失感と、実は外側に消えたのではなく自分の内に保有している、自分の一部であるという両義性を表現したいと思いました。自分の抱いた感覚や印象は、近づいたり遠くなったりしているけれど、意識するたびに誰でも感じ取れるという思いを込めています。
─ 作品を見る人々が、個々のコラージュからストーリーを作り出したら面白そうですね。白い背景が、見る人に想像させる余白のようにも感じられました。
そうですね。この白は無の空間、絶望的で計り知れない広がりを表しています。宇宙空間やパソコン内の膨大なデータベースなど、実体があるようでないようなものになぞらえています。実物の作品を見てくださった方には、自由にイメージを重ねていただけたら嬉しく思います。

掴みきれなさをコラージュで表現
─ 小さなコラージュでこのような大きな作品はあまりないのではないでしょうか?
当初は、絵の具の色の重なりで表現するようなことをすべてコラージュで描画しようかと想定していました。けれど、実際に貼っていくと隙や余白が活きて、大きい画面に対して小さな細かいコラージュというアンバランスさも想定を超える面白さになりました。自分の中のコラージュ作品への固定観念を逸脱できたかなと思います。
展覧会では、一つひとつのかけらを実際に目で見ていただいて、普段無意識に切り取っているような、その人の頭の中に浮かぶイメージと混じり合ったら嬉しいなと思います。

─ 今後はどのように活動していきたいですか?
楽しみながらいろいろな素材を選んで作っていきたいです。卒業後は平面作品と並行して、立体やデジタルコラージュから派生した映像などのインスタレーションも手がけてきました。これからもさまざまな媒体で制作し、発信していきたいと思っています。
─ 今回の審査員の講評では、写真や版画、そのほかのメディウムを効果的に用いた作品など、従来の絵画にとどまらない平面作品を望む声もありました。そうした審査員の目を、過去にたどったものなどを集散したコラージュという手法で、絵画への批評性も兼ね備えた笹本さんの作品が捉えたのかもしれませんね。
ありがとうございます。これまでの受賞作品がペインタリーで、絵の具の色彩の重なりを展開させるものが選ばれることが多い印象があったので、自分のようなアプローチを面白く感じてくださったことが嬉しかったです。
─ これからIdemitsu Art Awardに応募される方にメッセージをお願いします。
自分の作品の方が面白いという確信を持つことは、作品作りの要の一つだと思います。もし入選できなくても、一つの結果を自分の制作の材料にして、次につながる収穫になる場合もあります。そのためにも、自分にとって面白いと思うことに実直に徹底して作ることが大切だと実感できました。
アートの最前線を見つめるキュレーターや、作り手であるアーティストが審査員にいることもIdemitsu Art Awardの魅力です。新しい景色が見えるような作品をぶつけ合うことでアートシーンの活性化にもつながるのではないかとも思います。

初出:コンテスト情報サイト『登竜門』
取材・文:白坂由里 写真:加藤雄太
編集:岩渕真理子(JDN)