



使用済みプラスチックリサイクル
- 省資源・資源循環
リサイクルが難しい使用済みプラスチックを原油に近い状態まで分解する「油化技術」に、パートナー企業と連携して挑戦。石油化学製品や燃料油の原料として循環させることを目指します。

出光興産の製造拠点の一部では、石油精製を行う製油所と石油化学品の製造を行う化学工場が同じ敷地内に立地しています。これにより、石油精製から石油化学品の製造までを一気通貫して行えることが強みです。便利な生活を支える「プラスチック製品」の材料を提供する一方、未来の地球環境を守る責任も出光にはあると考えています。
長年にわたる石油精製・石油化学品の製造で培った知見と装置を活用し、リサイクルが難しいとされてきた、複数のプラスチックが混在する使用済みプラスチックを原油に近い状態まで分解する「油化技術」に挑戦しています。「ケミカルリサイクル」と呼ばれる手法の1つで、既存のインフラを活用して循環型社会に転換できる取り組みであると注目されています。
長年にわたる石油精製・石油化学品の製造で培った知見と装置を活用し、リサイクルが難しいとされてきた、複数のプラスチックが混在する使用済みプラスチックを原油に近い状態まで分解する「油化技術」に挑戦しています。「ケミカルリサイクル」と呼ばれる手法の1つで、既存のインフラを活用して循環型社会に転換できる取り組みであると注目されています。
使用済みプラスチックを取り巻く状況
私たちの生活と切り離すことができないプラスチック製品。日本国内で一年間に廃棄されるプラスチックは800万トン以上にものぼりますが、資源として再利用されているのはわずか20%。
50%以上がサーマルリサイクル(燃料に転用し、エネルギー源として活用する方法)されていて、CO₂の排出による影響が懸念されています。気候変動や海洋プラスチック問題への関心が高まる中、効率的にリサイクルし、資源として循環させていくことが求められています。
50%以上がサーマルリサイクル(燃料に転用し、エネルギー源として活用する方法)されていて、CO₂の排出による影響が懸念されています。気候変動や海洋プラスチック問題への関心が高まる中、効率的にリサイクルし、資源として循環させていくことが求められています。
Idemitsuが挑戦する理由と強み
油化技術への挑戦はかねてからなされてきましたが、コストや安全面がネックとなって商業化には至りませんでした。石油精製から石油化学品の製造まで一気通貫して手掛けてきた当社には、危険物を扱うノウハウや知見、インフラがあります。パートナ—企業との連携の上、我々だからこそ挑戦できる取り組みだと考えています。使用済みプラスチックを原油に近い状態まで分解したのち、石油化学製品や燃料油の原料として循環させるためには、石油精製・石油化学品の製造で培ってきた出光の経験とインフラが欠かせません。
今後の展開
環境エネルギー社と2019年から使用済みプラスチックの「油化技術」開発に取り組み、2021年からは実証検討を行ってきました。2023年4月には、当社の千葉事業所隣接エリアにて、油化ケミカルリサイクル商業生産設備への投資を決定しました。
具体的には、油化ケミカルリサイクル装置を建設し、プラスチックを油化することで得られた生成油を千葉事業所の石油精製・石油化学装置で精製・分解・重合し、「リニューアブル化学品」や「リニューアブル燃料」を生産します。2025年度下期の完工を予定しており、年間2万tの使用済みプラスチックの処理を目指します。
2023年10月には、竹中工務店の建設現場で発生した使用済みプラスチックの原料化に向けて、実証実験を開始することを発表しました。当社の子会社であるケミカルリサイクル・ジャパン株式会社が生産する生成油を、石油化学製品や燃料油の原料として利用できるかを確認するとともに、再資源化の可能性についても検証していきます。
資源循環はもちろんバイオマスプラスチックのサプライチェーン構築にも乗り出しており、材料の開発においてもカーボンニュートラル・資源循環への貢献に挑戦しています。
※2025年8月8日時点
具体的には、油化ケミカルリサイクル装置を建設し、プラスチックを油化することで得られた生成油を千葉事業所の石油精製・石油化学装置で精製・分解・重合し、「リニューアブル化学品」や「リニューアブル燃料」を生産します。2025年度下期の完工を予定しており、年間2万tの使用済みプラスチックの処理を目指します。
2023年10月には、竹中工務店の建設現場で発生した使用済みプラスチックの原料化に向けて、実証実験を開始することを発表しました。当社の子会社であるケミカルリサイクル・ジャパン株式会社が生産する生成油を、石油化学製品や燃料油の原料として利用できるかを確認するとともに、再資源化の可能性についても検証していきます。
資源循環はもちろんバイオマスプラスチックのサプライチェーン構築にも乗り出しており、材料の開発においてもカーボンニュートラル・資源循環への貢献に挑戦しています。
※2025年8月8日時点
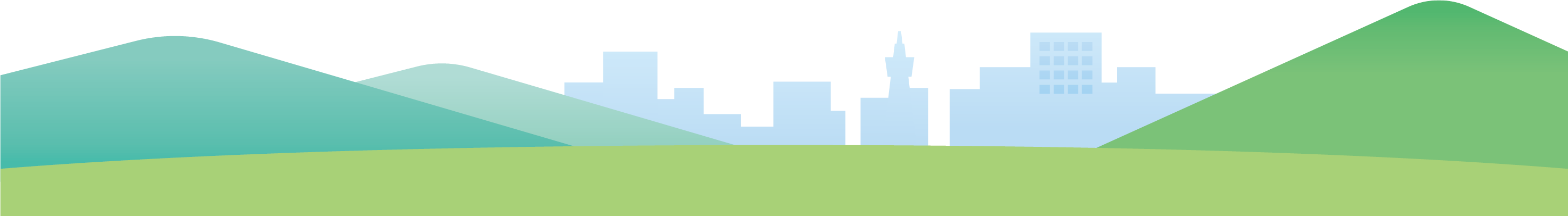
 戻る
戻る